SNSを中心に急速に広まった「予後悪ビンゴ」という言葉。
もともとは医療用語である「予後が悪い(=回復の見込みが低い)」という表現をもじり、ネガティブな特徴や体調不良を“ビンゴ形式”で並べることで共感や笑いを誘うミームとして使われてきました。
予後悪ビンゴは、一見すると軽い自虐ネタのようにも見えますが、その背景には現代のストレス社会や、SNS特有の“ゆるい共感文化”が見え隠れしています。
同時に、精神的な苦しみや病気を「ネタ化」してしまう危うさや、医療現場とのギャップが指摘されるケースも少なくありません。
この記事では、予後悪ビンゴとは何か、具体的にどのような内容が含まれているのか、そしてその社会的影響について、丁寧に紐解いていきます。
予後悪ビンゴとは?
「予後悪ビンゴ」とは、自分のネガティブな特徴をビンゴ形式で並べて、笑いや共感を誘うSNS発のネットミームです。
本来「予後が悪い」というのは、医学用語で「病気やけがの回復の見通しがよくない」ことを意味します。
ですが、「予後悪ビンゴ」はこの専門的な表現を日常的なユーモアに転用したものです。
2023年ごろからX(旧Twitter)を中心に流行し、自律神経の乱れ、不眠、家族関係のストレス、完璧主義など、心身に関わる“回復しづらそうな項目”をビンゴのマス目に並べて投稿する形式が広まりました。
予後悪ビンゴは、「自分、けっこう詰んでるかも」といった自虐的な笑いと、似たような悩みを持つ人同士のゆるい共感を生み出すコンテンツとして注目されました。
しかし同時に、「本来の医療用語を軽く扱っているのではないか?」という倫理的な批判も多く見られます。
ネット上の文化としては興味深く、自己表現の一つとも言える予後悪ビンゴ。
その意味や背景を知ることで、単なる“ネタ”以上の側面が見えてきます。
予後悪ビンゴの具体的な例
予後悪ビンゴは、自分の「心や体の不調に関する特徴」をビンゴの形式で並べてチェックする、SNS発の自己診断ミームです。
SNS上では、ビンゴカードのテンプレートに日常的な不調や生きづらさの要素が並べられ、自分に当てはまるものを塗りつぶしていく形で使われます。
ビンゴが成立すると「予後悪ビンゴ完成!」と投稿するのがお決まりの流れです。
一見ユーモラスなこの遊びは、「共感」を得る一方で、「病気や障がいを軽く扱っているのではないか?」という批判も多く、議論を呼んでいます。
予後悪ビンゴの典型的なマス目例
以下のような項目が多くのテンプレートで共通して見られます。
- 自律神経が弱い
- 睡眠リズムが崩れている
- 精神科・心療内科の通院歴がある
- 両親または家族との関係が悪い
- いつも疲れている/慢性的な倦怠感
- 対人関係に強いストレスを感じる
- 食生活が乱れている(朝食を抜く、偏食など)
- 体調が悪くても我慢してしまう
- 思考がネガティブになりやすい
- 完璧主義で自分を追い詰めがち
- 他人に弱音を吐けない
- 家から出るのがつらい/引きこもりがち
- 病院に行かず、不調を放置しがち
- 低血圧・貧血・めまいなどが頻発する
- 気圧や季節変化で体調を崩しやすい
これらはすべて、「一つひとつは小さな不調でも、積み重なると予後(今後の健康状態)が悪くなりやすい」ことを連想させる特徴です。
「ネタ」としての軽さと、含まれる重さ
このような予後悪ビンゴは、投稿者自身が自分の弱さやしんどさを“ネタにして笑う”自虐スタイルで共有するため、一部のユーザーには「共感できて安心する」「同じような人がいて救われる」といった反応もあります。
しかし同時に、「実際にその項目に苦しんでいる人たちにとっては不快」「精神疾患や障がいを“笑いもの”にしている」と感じる声も多く上がっています。
特に、医療関係者やメンタルヘルスに関心のある人たちからは、「本来“予後が悪い”という深刻な医療用語をミーム化すること自体に問題がある」といった指摘もあります。
なぜこれが「予後悪」なのか?
本来「予後が悪い」とは、医学的に「病状が長引く、あるいは回復の見込みが低い」とされる状態を指します。
予後悪ビンゴはそれをもじり、「この状態が続くと人生の見通しもつらくなりそう」という皮肉的・ユーモラスな自己表現に変換しています。
とはいえ、実際には慢性的な心身の不調を表すリアルなリストでもあるため、見る人によっては重く、また不快に映ることもあるのです。
予後悪ビンゴは、ただのネットの流行語ではなく、「共感」「自虐」「誤解」「批判」が交錯する複雑な表現です。
具体例を知ることで、その背景や受け止め方の違いがより理解しやすくなるでしょう。
予後悪ビンゴの影響と一部で受け入れられていた理由
予後悪ビンゴは、気軽なミームの形をとりながらも、実際には当事者や医療現場にさまざまな影響を与えるデリケートな表現です。
SNSで話題になった予後悪ビンゴは、自分の弱さをネタ化して共有できるコンテンツとして広まりましたが、それによって心の病気や身体的な不調が「笑われるもの」として扱われる危険性が指摘されています。
とくに、うつ病や自律神経失調症、発達障害など「目に見えにくい不調」を抱える人にとって、予後悪ビンゴの軽さは自分の苦しみが軽視されているように感じられることがあります。
また、「予後が悪い」という医学的な表現が軽々しく使われることで、重い病気の診断を受けている患者にとっては精神的な負担にもなりかねません。
予後悪ビンゴの拡散は、当事者が支援や理解を求めづらくなる状況をつくり、社会的な偏見(スティグマ)を助長する可能性があるとも言われています。
一方で、予後悪ビンゴがすべて否定されているわけではありません。実は、この言葉や形式が一部で受け入れられていた背景もあります。
一部で受け入れられていた理由
- ストレス発散の手段として
予後悪ビンゴは、つらい状態を言語化し、あえて笑いに変えることで心を軽くする「ブラックユーモア」として使われていました。
とくに医療者やしんどさを抱える人たちにとって、「ネタにしてでも生き延びる」姿勢の表れでもあります。
- 似た者同士の共感ツールとして
予後悪ビンゴは、「自分だけじゃなかった」と感じられるツールでもありました。
不調を抱える人同士が共通項を見つけ、孤独感をやわらげる目的で投稿するケースも少なくありません。
- 本来は内輪のコンテンツだった
もともとは閉じたコミュニティ内で使われていた表現が、SNSで急速に拡散されたことで批判を招いたという経緯もあります。
意図せず「公の目」にさらされたことで、受け取り方に大きなギャップが生じました。
予後悪ビンゴは、「ユーモア」と「無神経」の間にある微妙なラインを問う存在です。
見る側の背景や立場によって感じ方が大きく変わるからこそ、言葉の扱いには慎重さが求められます。
それでもなお、予後悪ビンゴという言葉が広がった背景には、人がしんどさを共有したい、誰かとつながりたいという根源的な欲求があることも忘れてはいけません。
まとめ
予後悪ビンゴは、SNSを中心に広がった自己分析型のミームであり、ネガティブな特徴や心身の不調をビンゴ形式で可視化するというユニークなスタイルが話題となりました。
一方で、「予後が悪い」という本来は深刻な医療用語を軽く扱っているとして、批判の声も多く上がっています。
予後悪ビンゴに共感し救われる人がいる一方で、傷ついたり違和感を覚える人がいるのも事実です。
予後悪ビンゴが示しているのは、現代社会における孤独やストレス、そして「共感の場」を求める人々の心の動きなのかもしれません。
この言葉に触れるときは、軽さの裏にある重みや、表現の影響力についても考える視点を持っておきたいものです。

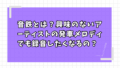
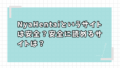
コメント